
「このまま、3年間ずっと同じ中学校に通わせるのは無理かもしれないな」
そう実感したのは、小学6年生の進路を本格的に考え始めた頃でした。
私たちは転勤族。引っ越しの時期や場所はコントロールできません。どれだけ子どものことを考えて学校を選んだとしても、中2・中3のタイミングで転校する可能性は常にあるのです。
特に、思春期の男の子がその環境の変化にどう対応できるのか。親としては、正直とても心配でした。
「それなら、いっそ東京の祖父母の家に下宿して、安定した中学生活を送らせるのも一つかもしれない」
そう考えたこともありました。でも、実際に想像してみると、東京の中学校に地方から編入することの不安は大きい。
知っている子は一人もいない。
文化もスピードも違う。
「方言をからかわれるんじゃないか?」
「田舎者って思われるんじゃないか?」
そんな心配が次々に浮かんできて、最終的に「それなら別の選択肢を探そう」と思ったのです。
「海外に行ってみたい」と言っていた長男の言葉
実は、長男は小さな頃から海外に興味を持っている子でした。
「エジプトのピラミッド、見てみたいな」
「ブラジルのカーニバル、楽しそう」
「いつか世界一周の旅に行きたい!」
そんな夢のような言葉を、何の前触れもなくぽろっと言うような子。
親として「海外に行け」と言ったことは一度もありません。それでも自然と“世界の広さ”に惹かれているように感じていました。
地元の外へ出てみて、気づいたこと
小5からは地元ではないエリアにある進学塾に通うようになり、そこで出会った友達から大きな刺激を受けたようです。
「同じ小学生なのに、あの子たちは自分の進路や将来についてすごく真剣に考えてる」
「勉強に対する姿勢も、家族との関係も、いろんな価値観があるって初めてわかった」
地元の小学校しか知らなかった世界から、少し外に出てみただけで、視野がぐんと広がったようでした。
そんな彼が「地元の中学には進学したくない」と言い出したのも、この頃でした。
だから「単身留学」が現実的な選択肢になった
「どうせ転校するなら、まったく違う世界に飛び込んでみたい」
その想いが彼の中で強くなってきた時、マレーシアの単身留学という選択肢が、現実味を帯びて見えてきました。
英語のレッスンも、自分から進んで毎日受けるようになり、
「今日は英語でこんなこと言えたよ!」と笑顔で報告してくれる日々。
もちろん、心配がなかったわけではありません。
「まだ小学生なのに、ひとりで海外生活なんてできるのか」
「寂しくないのか」
「言葉の壁にぶつかって、つらい思いをしないか」
でも、一緒に悩み、一緒に準備を進めていく中で、家族としての絆がより深まっていったようにも感じています。
「今のうちに」じゃないとできないこと
次男と三男は、今のところ海外にも英語にもあまり興味を示していません。
彼らにとって留学は“現実的ではない選択”だと思っています。
だからこそ、長男の「今」のタイミングを逃したくなかった。
本人の希望と、家庭の環境、そして転勤族という状況。
いろんな条件が重なったからこそ選べた「単身留学」という道。
この選択が、彼にとって、そして私たち家族にとって、これから先を強く生き抜く糧になることを信じています。


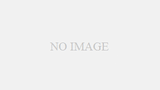
コメント