
「海外留学をさせたい」と考え始めたとき、私たち親子にとって、最初の大きなテーマは「どこの国に行くか?」でした。
小学生が単身で生活し、学ぶことができる国。しかも、安心・安全で、英語環境があり、かつ学費や生活費が現実的であること——これらを満たす国は、実はそれほど多くはありません。
候補に挙がったのはこの5ヶ国
私たちが最初に検討したのは、次のような国々でした。
- シンガポール
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- マレーシア
いずれも英語が通じ、留学生の受け入れ体制が整っている国ばかりです。
でも、現実的に「小学生の単身留学」という視点で調べていくと、意外なことに気づきました。どの国にもそれぞれ“壁”があったのです。
シンガポールは魅力的だけど…
まず最初に思い浮かんだのは、シンガポール。教育水準も高く、治安も良好。日本人にも人気の国です。
でも、調べてみると、
- 学費が非常に高額(年間200〜300万円以上)
- 現地校への入学難易度が高い
- そもそも小学生の寮生活が難しい
という現実が立ちはだかりました。
特に、現地校の入学試験は英語と中国語が両方必要なことが多く、10歳前後の日本人の子どもにとってはハードルが高い印象を受けました。
オーストラリア・ニュージーランドは理想だけど遠い
続いて検討したのは、オーストラリアとニュージーランド。
自然豊かで、教育にも余裕があり、「のびのびとした学び」が実現できそうだと思いました。実際、小学生向けのボーディングスクール(寮制の学校)も存在します。
ただ、気になったのは次の点。
- 渡航距離が遠く、親がすぐに会いに行けない
- 航空券や生活費などのトータルコストが高め
- 医療や生活インフラへのアクセスに不安がある地域もある
万が一、何かあったときに「すぐに駆けつけられない」距離感が、やはり親としては気がかりでした。
カナダも人気だけど、小学生には選択肢が少ない
カナダは、教育レベルが高く、多様性を重んじる文化があり、留学先としては非常に人気です。
ただ、実際に調べてみると、
- 小学生の受け入れ先が非常に限られている
- 住居をどうするか(親が帯同する必要があるケースが多い)
- 英語力の要求レベルが高い学校もある
という課題がありました。
中高生なら選択肢が広がる国ですが、「小6で単身留学」となると、やや現実味に欠けると感じました。
なぜマレーシアだったのか?
こうした中で、どんどん選択肢が絞られていき、最終的に浮かび上がってきたのが「マレーシア」でした。
正直、当初は「本当にマレーシアでいいの?」という気持ちもありました。日本ではまだ馴染みが薄く、情報も少ない。でも、調べれば調べるほど、「ここならいけるかも」と思える要素が次々に出てきたのです。
マレーシアが持つ“5つの魅力”
- 教育水準が高く、選択肢が多い
イギリス式、アメリカ式、オーストラリア式など、多様なカリキュラムを選べるインターナショナルスクールが充実しています。 - 学費・生活費が比較的リーズナブル
インター校の年間学費は80〜150万円程度と、他国に比べて手が届きやすい水準。生活費も日本の1/2〜1/3程度。 - 英語が公用語のひとつ
多民族国家であるマレーシアでは、マレー語・中国語・タミル語と並んで、英語も日常的に使われています。 - 治安が比較的良く、日本人も多い
首都クアラルンプールには日本人学校や日本人医師のいる病院もあり、万が一のときも安心感があります。 - 時差が1時間。親が行き来しやすい
日本から約7時間のフライト。時差もわずか1時間で、親がサポートしやすい距離感です。
小学生の“単身留学”が現実的にできる国
実はマレーシアには、小学生を対象とした「寮付きのインターナショナルスクール」がいくつか存在します。
寮では24時間体制でスタッフが見守ってくれ、生活面のサポートも整っている。しかも、多くの学校が全寮制ではなく、途中で親が訪問したり、短期で帰省したりできる柔軟な体制をとっています。
「親元を離れる」といっても、極端に突き放すような形ではなく、必要に応じて寄り添える距離感。この絶妙なバランスが、私たち家族にとってはとても魅力的でした。
子どもにとって“楽しい未来”を想像できたかどうか
最終的な決め手は、親の都合ではなく、「子どもにとって、ワクワクする未来が想像できるか」でした。
マレーシアにある寮の写真を見せると、息子は
「めっちゃホテルみたいじゃん!行ってみたい!」と目を輝かせました。
学校の食事がビュッフェスタイルであること、世界中の友達と友達になれること、放課後にプールやスポーツ施設が使えること——そうした“楽しそう”な要素を感じられたことが、何より大きかったと思います。


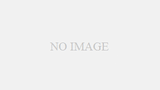

コメント